独自基準とりやめについての一般質問をAIに整理してもらった
- 佐藤たつ

- 2024年12月9日
- 読了時間: 5分

2024年12月定例会の、小学1,2年生の少人数学級独自基準のとりやめについての一般質問をAIに整理してもらいました。使用したAIは
整理につかったもの
使ったAI
GoogleのGeminiです。Gemini Advanced 1.5 proを利用しました。
資料
2024年12月4日総務文教常任委員会資料の一部(資料3)
2024年12月6日の一般質問の書き起こし
書き起こしのつくりかた
議会中継のyoutubeを自動文字起こしサービスNottaで文字起こし
文字起こししたテキストをGeminiで整形(一部手直し)
※この書き起こしは正式な議事録ではなく、内容の正確性を保証するものでもありません。
では、Geminiの整理をみてみましょう!明らかな誤りは修正しています。
スライドにしてみました。
このスライドは、後掲のテキストをもとにスライド生成AI Gammmaでつくったものです。
議論の整理
独自基準とは、当別町一体型義務教育学校基本構想において、少人数・習熟度別による丁寧な指導を充実させるために、1年生と2年生の定数を29人に設定した学級編制の基準のこと。
独自基準取りやめの説明資料20241204_総務文教常任委員会.pdfの「検討結果」と202412一般質問要点書き起こしにおける議論を照らし合わせ、独自基準の取りやめに関する教育委員会側の根拠を以下の表にまとめました。
根拠 | 資料における説明 | 議論における説明 | 妥当性 |
基本構想策定当初は、学級編制の基準に達することがなく、独自基準を適用することがなかった | 策定時には、各学年2クラスの18学級編制を想定していたが、実際には基準に達することがなかった | ― | 資料に記載されている通り |
学習指導要領が改訂され、主体的・対話的で深い学びと協働的な学びを進める上で、少人数化が必ずしもプラスに働かない場合もある | 少人数化よりも複数指導体制の方が有効 | 少人数化と対話的な学びの充実度は関係ないのではないかという質問に対し、教育長は「子供たちの様子というのは非常に多様化しており、そういう中で、その多様化したお子さんにですね、寄り添っていく事業を行うためには、たくさんの人員が必要だということで、そのために手厚い指導員だとか、それから補助をする方々が必要だということ」と答弁している。 | 資料の記載に加え、多様な児童生徒への対応という根拠を提示している |
令和元年以降、学力向上が成果となってあらわれている | 学力向上は成果となって現れている | ― | 資料に記載されている通り |
現在の当別型複数指導体制は、多様な児童生徒に寄り添った、行き届いた指導ができ、学校の状況によって職員配置を変更することが可能 | ― | 現在の当別型複数指導体制の方が、今の教育指導要領に合っていて、しかも当別の教育に合っている。そして成果が上がっていると教育長は答弁している。 | 資料には記載されていない、新たな根拠を議論で提示している |
議論の要点
独自基準と複数指導体制に関する議論
教育委員会側は、独自基準と複数指導体制は二者択一ではなく、予算規模や人材確保の観点から複数指導体制を選択したと説明。
質問者は、独自基準をベースとした検討が十分に行われていないのではないかと指摘。
学習指導要領の改訂に関する議論
教育委員会側は、学習指導要領の改訂を踏まえ、主体的・対話的で深い学びと協働的な学びに適した複数指導体制を選択したと説明。
質問者は、独自基準策定時に新学習指導要領の内容が考慮されていたのか疑問を呈し、学習指導要領の改訂を根拠とするのは適切ではないと指摘。
総合教育会議における教育長発言に関する議論
教育委員会側は、総合教育会議での教育長発言は、先生方の意見を踏まえたものであると説明。
質問者は、保護者や児童生徒への意見聴取が行われたのか疑問を呈す。
西当別小学校の教室の狭さに関する議論
教育委員会側は、西当別小学校の教室の狭さを認識しており、次年度以降対応していくと説明。
質問者は、具体的な対策とスケジュールを求める。
西当別地区の義務教育学校化に関する議論
教育委員会側は、西当別地区の義務教育学校化については、2023年3月定例会一般質問での答弁と認識は変わっていないと説明。
保護者への説明に関する議論
教育委員会側は、要望書の代表者に対して書面と説明をもって回答すると説明。
質問者は、全保護者を対象とした説明の必要性を指摘。
まとめ
教育委員会側は、独自基準の取りやめについて、資料で示した根拠に加え、多様な児童生徒への対応や現状の複数指導体制の有効性などを根拠としています。しかし、質問者からの指摘にもあるように、独自基準策定時に新学習指導要領の内容をどこまで考慮していたのか、また、独自基準をベースとした検討が十分に行われたのかについては、議論の余地が残るところです。
せっかくなので、Geminiに質問者、答弁者(教育委員会)双方の良かった点、改善すべき元を聞いてみました。
この内容は、あくまでGeminiが作成したものをそのまま掲載してます。
質問者の良かった点
論理的な質問: 6月の答弁との矛盾点を突くなど、論理的な質問で教育委員会の説明の根拠を揺さぶろうとしていた。
具体的な質問: 教室の狭さ対策など、具体的な質問で教育委員会の対応を迫っていた。
多角的な視点: 子供、保護者、教員の視点を取り入れ、多角的な視点から質問を行っていた。
質問者の改善が必要な点
質問の焦点: 質問の焦点が絞り切れず、議論が発散してしまう場面があった。
質問の意図: 質問の意図が伝わりにくい場面があり、教育委員会側との認識のずれが生じていた。
教育委員会の良かった点
丁寧な説明: 質問に対して、可能な限り丁寧に説明しようとする姿勢が見られた。
根拠の提示: 独自基準の取りやめについて、複数の根拠を提示していた。
教育委員会の改善が必要な点
説明の明確さ: 質問への回答が曖昧で、分かりにくい説明があった。
説明の一貫性: 6月の答弁との整合性が取れていない説明があった。
根拠の具体性: 根拠として示されたデータや数値が不足していた。
改善点に関する補足
質問者と教育委員会双方とも、議論の前提や認識にずれがあるように見受けられました。事前の情報共有や議論の構造化など、相互理解を深めるための工夫が必要と考えられます。














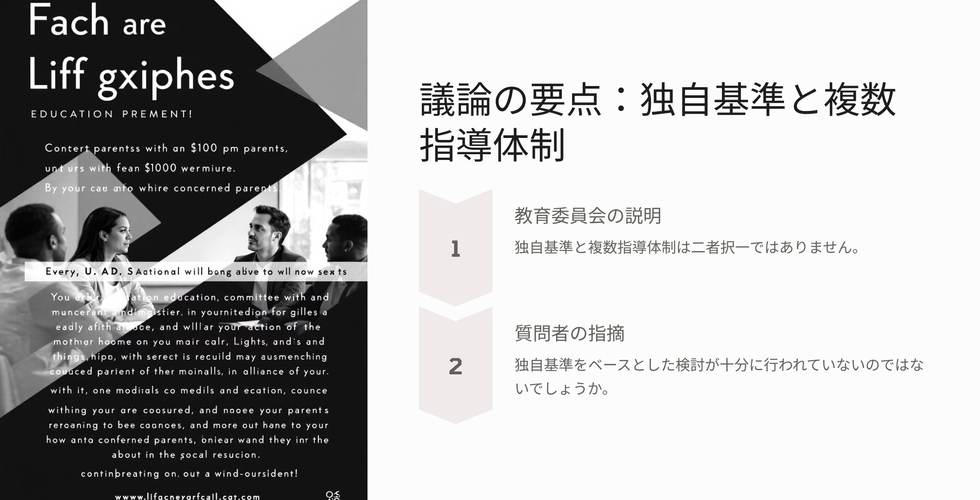









コメント